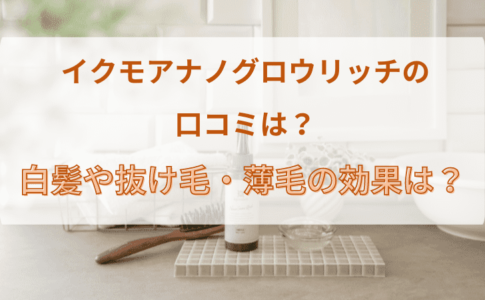端午の節句。5月5日のこどもの日。子どもたちにとって嬉しい日です。
パパやママがこどもの日に買ってあげると約束したモノが手に入る…。
子供にとっては欲しいものが買ってもらえて、自分の好きは料理を作ってもらえるかレストランへ行く。。。
端午の節句の由来や、どんな行事かは関係ないんですよね♪
今回は「端午の節句ってそもそもどんな行事?柏餅やちまきを食べるのはなぜ?」
と題して
ということについてまとめていきます。
子どもはさておき、大人は端午の節句について少しは知っておきたいですね。
それではそれではさっそく本題へ入っていきましょう。
目次
端午の節句ってどんな行事?

端午の節句は五節句のひとつで、桃の節句(3月3日)や七夕(7月7日)と同じく、古来から日本や中国で大事にされてきた行事です。
厄除け行事が男の子のお祝いに
端午の節句は、日本においては奈良時代から続く行事です。
季節の変わり目に、厄除けの意味を持つ菖蒲を飾ったり、薬草であるヨモギを配ったりして、病気や災厄から身を守るという意味を持った宮中行事だったんです。
端午の節句に柏餅やちまきを食べるのはなぜ?

端午の節句に欠かせない食べ物である柏餅やちまきですが、これらを食べるようになった理由をご存知ですか?
端午の節句にこれらを食べるようになったのにはちゃんと理由があるんです。
端午の節句の代表的な行事食は、あんなどの入った餅を、柏の葉で包んだ「柏餅(かしわもち)」と、笹の葉で細長いお団子を包んだ「ちまき」です。柏餅とちまきのどちらを食べるかは、地域によって違いがあるようです
端午の節句に柏餅を食べるのはなぜ?

柏餅は子孫繁栄を願って食べるもの。
柏餅が食べられるようになったのは江戸時代(徳川9代将軍~10代将軍の頃)と云われています。
柏餅に使われている【かしわ】ですが、この植物にはある特徴があります。
その特徴とは≪新芽が育つまで古い葉が落ちる事が無い≫というものです。
この事から子供が育つまで親が死ぬことは無い、つまり家系が途切れる事なく繁栄するというゲン担ぎです。
かしわの葉を使った柏餅を武家階級の方がお家の繁栄を願い好んで食べていたとされています。
その為、縁起物としてかしわの葉を使いお餅を包んだ柏餅という和菓子が出来たのです。
関東では「柏餅」、関西では「ちまき」がよく食べられてきました。
近年は柏餅が全国的になりつつありますが、そもそもは関東を中心に柏餅が、関西を中心にちまきが食べられてきました。
関東でちまきといえば、おこわを竹皮で三角形に包んだいわゆる中華ちまきのことを指すのが一般的ですが、特に端午の節句に食べる習慣はないようです。

関西で端午の節句に食べられる「ちまき」は、笹の葉にほんのり甘いお団子を包んだ細長い和菓子が一般的です。
端午の節句にちまきを食べるのはなぜ?

ちまきは端午の節句行事とともに中国から伝わったもの。
中国の故事からきており、難を避ける厄払いの力があるとされ、最初は、楝樹(れんじゅ)の葉でもち米を包んでいたそうです。
時代が下ると、茅(ちがや)の葉も使われるようになり、「ちがやまき」とも呼ばれ、それがだんだんと短縮され、ちまきと呼ばれるようになりました。
「ちまき」は中国の「屈原(くつげん)」の故事がもとになって「端午の節句」に食べるようになり、後に日本でも食べられるようになりました。
ちまきを食べる風習が関西方面に多い理由は、端午の節句が中国から伝わった奈良時代の都がその地域だったからです。
中国戦国時代の屈原の伝説は以下になります。
戦国時代の中国に楚という国があり、そこにとても博識で政治的手腕にもすぐれた屈原という男がいました。
この屈原は王の信頼も厚く側近となっていたのですが、他の官僚の陰謀によりその地位から失脚してしまいます。
その後、楚が敵国である秦軍に攻め落とされた事から楚の行く末に絶望し汨羅江(べきらこう)へと身を投げ入れました。
屈原は人々からの人望も厚かった為、屈原の死を知った人々は彼の亡骸が魚に食べられる事が無いようにと、魚の餌にもなる粽(ちまき)
を汨羅江へと投げ入れたのがちまきの始まりと云われています。
この屈原の命日が5月5日であった事から、端午の節句と粽(ちまき)が結びついて日本へと伝わったとされています。
端午の節句のお祝い料理は他に何があるのか?
端午の節句には柏餅やちまきというのは有名ですので、多くの方が知っています。
しかしこの日は男の子の健康と成長をお祝いする日なのに、柏餅やちまきだけというのもなんとなく寂しいですよね?
端午の節句には「これを絶対に食べる」という決まりはありませんが、せっかくなら特別な料理を用意したいですよね。
竹のようにまっすぐ元気に育ってほしいという願いが込められた筍。
“勝男”になぞらえられる鰹や、鱸(スズキ)、鰤(ブリ)のように、成長に合わせて呼び名が変わる出世魚。
これらは縁起の良い食べ物とされ、男の子の将来の活躍を願って端午の節句によく食べられています。
しかし、決まりがないのだから、風習に捉われないで、柏餅やちまき、ちらし寿司やケーキなどを用意してあげルほうが子どもは喜びますよね。
最近は、ちらし寿司やいなり寿司、ケーキなどでこいのぼりや兜をかたどった、「新しい端午の節句の行事食」も珍しくなくなりました。
そもそもお子さんのためのお祝いですので、お子さん自身が喜んでたべるものを、ということなのかもしれませんね。
まとめ
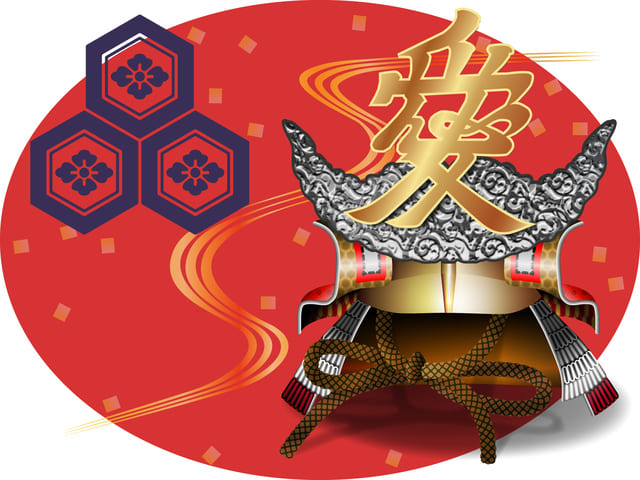
今回は「端午の節句ってそもそもどんな行事?柏餅やちまきを食べるのはなぜ?」と題してお伝えしました。
端午の節句に食べるのは当たり前だと思っていた【柏餅やちまき】もこのような理由があったのですね。
「筍(たけのこ)」や「鰹(かつお)」や「出世魚」が男の子の健やかな成長を願う食べ物だというのは言われてみれば納得がいきます。
しかし、子どものためのお祝いだから、子どもがよろこんで食べる料理を用意してあげたほうが喜んでくれますよね。
追記:五月人形はいつからいつまで飾るの?

飾り付けの時期は地域や家庭によって違いがありますが、一般的に4月に入ったタイミングで飾ることが多いようです。
前日や当日に飾るのは縁起が悪いとされているので、注意しましょう。
片付ける時期にも明確な決まりはありませんが、梅雨に入る5月中旬までには片付けたほうが、鎧や五月人形は湿気に弱いので、天気がいい日を選んで片付けるといいですよ。
鎧と着た五月人形は、鎧と同じように「大切なわが子が守られますように」という願いを込めて飾られます。
もともと平安時代には、子どもたちが紙で作ったかぶとをつけて遊ぶこともあったそうです。
時代が下ると、紙や木で作った菖蒲人形を庭先や室内に飾るようになり、人形の種類も増え、現在に続く風習が形作られていった……という説もあるようです♪
それでは、今回はここまでにさせて頂きます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました!







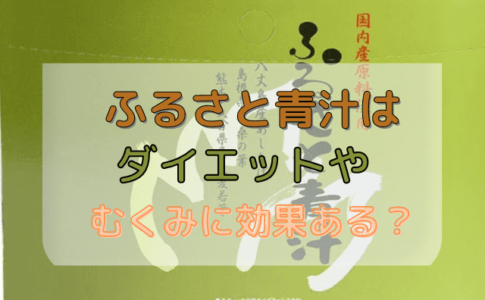
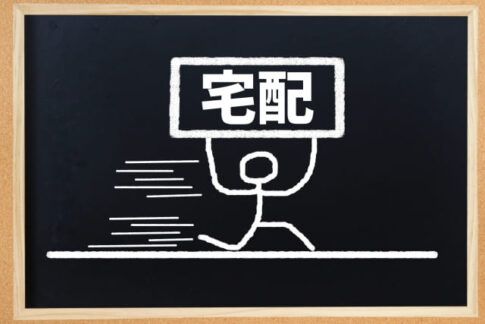


 kei
kei